活動方針(令和7年度)
空気が育む人と組織 ─方針なき方針─
一般社団法人 日本青少年育成協会 会長
増澤 空
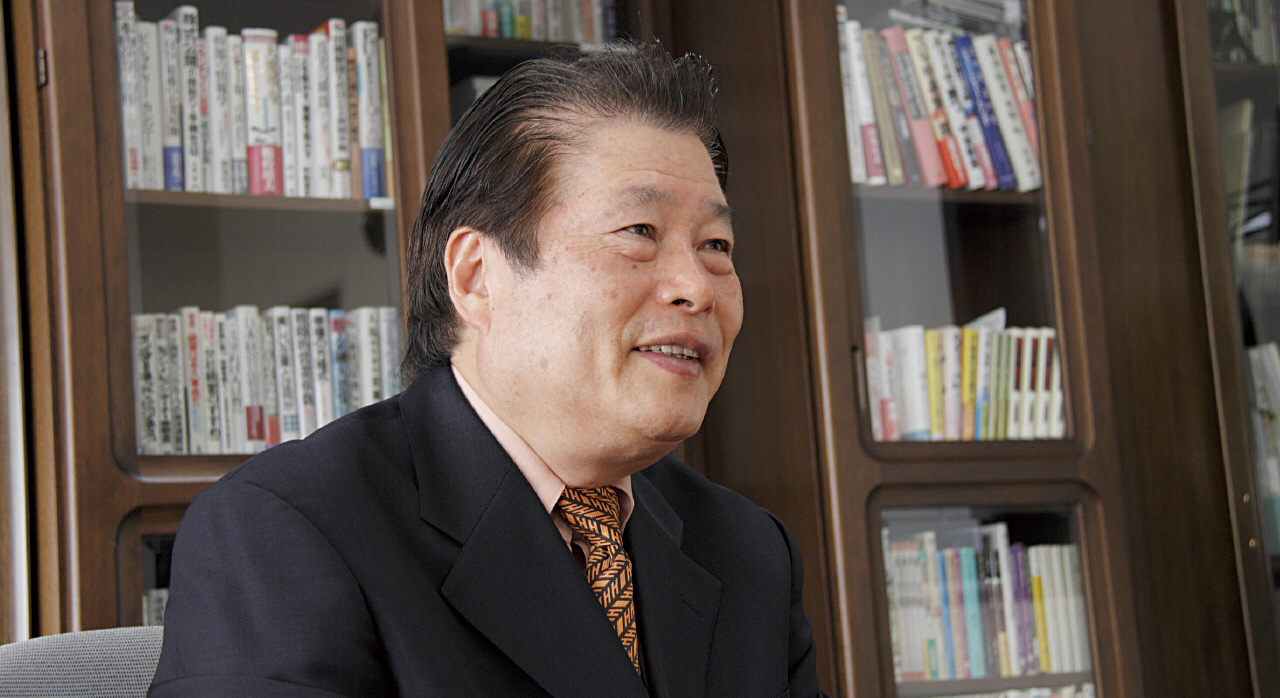
増澤会長
「本田さん、今回は私から一方的に方針を伝えるのではなく、対談形式で『来年度について』話をしませんか?「来年の方針はこうしましょう、方針がこうだからこうせねば」というやり方は、私は本来苦手なのです。
私が大事にしてきたもの、そしてこれからも大事にしていきたいものは、一言でいうと、「空気」なんです。弊社でも時折「空気の教育」という言葉で表現しております。会社でしたら「社風」、教室でしたら「校風」、地域でいうと「風土」、それらから生みだされる「文化」─このようなものを大切にしたいと思っております。
例えば教室を例にとってみると、授業が始まる前、誰も何も言わなくても生徒が自学自習に取り組んでいる教室もあれば、授業が始まるまでざわついている教室もあります。校風がそれを創り出しているのです。空気がそうしているわけです。いわば「空気が人を育てる」ということです。ですから今回は、お互いインタビュアになって質問しあいましょう。
日青協には11の委員会があり、立派な大人の集団なのですから、来年度の方針はその方々にお任せするのが一番だと考えております。皆さんはスーパーボランティア並みの動きで、報酬もない中、時間を創り出して毎回の理事会、総会、イベント等に集まって下さいます。そんな皆さんに「今年の方針はこうで、こうしなさい」というのは、そもそも私の性格に合いません。既に自ら動いていらっしゃいますので、我々のインタビューのやりとりを皆さんに発信し、あとは感じていただいて、それぞれの委員会で計画、企画、創造していただきたいというのが、私の正直な思いです。」
事務局長
「はい わかりました。会長いつも斬新なご提案ありがとうございます。」
増澤会長
「では最初に、私から本田事務局長にインタビューします。事務局長、今年を振り返ってどんな一年でしたか?どんな活動をやって、どんな感動がありましたか?」
事務局長
「以下のような活動でした。(一覧表参照)
印象深かったものを一つ上げるならば、なんといってもHSKフェアでした」
| 1月 | 愛媛のサッカークラプで岡田監督のスタジアムでの理事会 チャリティイベント |
| 3月 | オンライン留学 理事会 |
| 4月 | チャリティイベント 国際中文教師資格試験 |
| 5月 | 総会 宝槻様の講演会 チャリティイベント |
| 6月 | オンライン留学 国際中文教師資格試験 |
| 7月 | 新宿区後援事業 ワークショップ開催 五島市就職支援事業 入札 落札 オンライン留学 |
| 9月 | 国際中文教師資格試験 |
| 10月 | 19 日 HSK フェア 17 日セミナー 18 日セミナー 19 日フェア 19 日 異業種交流会 20 日 教育コミュニケーションフォーラム |
| 11月 | 世界中文大会参加 |
| 12月 | 教育コーチングトレーナー総会 華中科学技術大学短期留学サポート 南海大学短期留学サポート 国際中文教師資格試験 |
HSK試験/スポーツ委員会会議/国際交流勉強会と拡大会議/留学説明会/高校大学に出向いてHSK説明会
増澤会長
「どんなところが?」
事務局長
「9回目を迎え、さらに会場(大正大学)が昨年と同じということもあって、我々としては慣れているつもりでおりました。九分九厘準備が整いかけた開催日の2週間前くらいだったでしょうか。
中国側から「規模を大きくしなさい。VIP(中国大使、外務省や文科省はじめ約10名以上の来賓)をお迎えしてください」という要請がありました。そこからが大変で、私自身心の中では、今からできるわけがないという思い込みとの闘いでした。」
増澤会長
「そんな状況で感じたこと、感動したことは?」
事務局長
「結果、今では中国側からの要請を受け入れて本当によかったと思っております。」
増澤会長
「それは? どうして」
事務局長
「まず在日本国大使館 呉大使と文科省からの来賓、さらに関係機関約10名をお招きできたこと。SP付きの来賓は初めての経験でしたし、またVIPの方々同士も初対面でした。そんな緊張の中、会長の場づくり、空気づくりを間近で拝見できたことです。これは本当に大きかったです。リラックスした雰囲気にあって、厳格かつ笑顔あふれる式典がとり行われました。そこからの勢いが、フェア全体を成功へ導いたように思います。大使も来賓の皆様も試験会場、フェア会場をご覧くださいましたが、フェアの規模の大きさに驚かれて、予定時間をオーバーしても会場を見学しておられたことから、大変喜んでお帰りいただけたと思っております。日青協の存在をしっかりアピールできたように思います。」
増澤会長
「そうでしたか。そんな大変な感じは受けなかったですけどね。会場で一生懸命接客されるスタッフの皆さんの笑顔が印象的でしたよ。」
事務局長
「ありがとうございます。では会長、フェアの件で、こちらからもインタビューよろしいでしょうか?」
増澤会長
「いいですよ」
事務局長
「控室がとにかく明るかったですし、和やかでした。そこの中心にいらしたのは会長でした。意図的にやられていたのですか?」
増澤会長
「いやあーいつもと変わりなく、なんの企てもなく、コミュニケーションをとっていました。ただね、まったく知らない者同士でも集まって同じ目的で動くわけなので、元々通じ合えるものがあるんですよ。だから、こんなことは言ってはいけないとか言葉遣いがこうでないといけないとか全然考えず自分の言葉で、本音で接していただけです。」
事務局長
「そうですか。あの場づくりはなかなか表現しようがなく言葉が見つかりません。今回のインタビューを通してわかったのですが、空気づくりが意図的でなく自然体でしたから、初対面でも和やかな雰囲気を醸し出すことができたのですね。控室で創られた空気があったからこそ、冒頭の会長のスピーチから始まった式典が、一気に笑顔に包まれる流れとなりました。その結果フェア自体の大成功を収めることができました。会長が空気づくりにおいて、一番大事にしていらっしゃることは何ですか?」
増澤会長
「ん―――これをいうとねー振り出しに戻るんです。つまり言おうと思えば 言えないことはないんですが、相当な時間を要します。つまり全てなんです。それを文字で伝えてしまうと『こうしなさい、こうせねば』になってしまいます。冒頭にお伝えしたように、理事、委員長の皆さんは、ボランティアでかかわってくださる仲間です。会いたくなる仲間、このやり取りを読んでいただくことでわかりあえる方々です。だからこそ、その皆さんにお任せし、今まで通り皆さんの力で創り出していってほしいわけです。」
事務局長
「では 最後の質問ですが、令和7年はどんな年になりそうですか?」
増澤会長
「そうですね。日青協は、今でも空気ができていると思うんです。だから、会員が増加しているし、若い理事も多くいらっしゃる。若い方には思い切った企画をやっていただくのもいいですね。HSKフェアも11の委員会の一つですよね。「責任」や「志」を抱いてやっていることはわかりますが、我が社団はそれだけではないように感じています。まじめすぎる活動ではなかなかここまで続かないし、ボランティアでやっているからと言って、威張る人もいない。困っている人をみたら手を貸してあげる、それが当たり前でしょうという感覚の仲間であって、そういう仲間と交流したい、これでいいのではと思っています。ここに来たらそんな空気が漂う、そしてその空気を吸いに来たくなる空間ができればいいのではと思っております。
最後に、副会長の木村さんから、会員の皆さんたちのチャリティ基金がずいぶん増えてきたので、この基金を子どもたちのためにどのように使おうかという提案がありました。皆さんから、いろんな提案や活発な意見が飛び交い、本当にいい組織だなあとしみじみ思いました。「子ども食堂」や「離島における教育支援」など、来年への持ち越しになりましたが、空気が育む人の集団、ますますいろんな人、集団の方が参加されることを切に願っております。」
事務局長
「来年度(令和7年度)は日青協らしい空気漂う充実した年になりそうです。増澤会長、誠にありがとうございました。」




